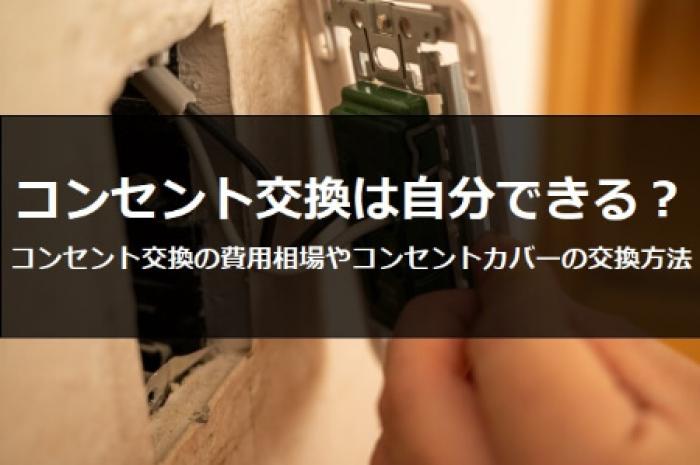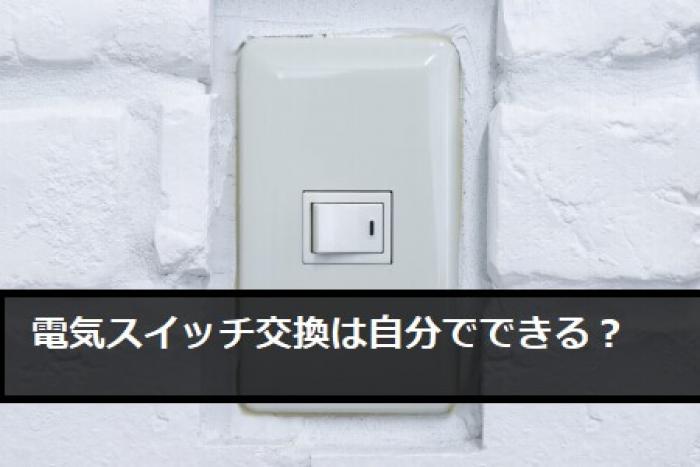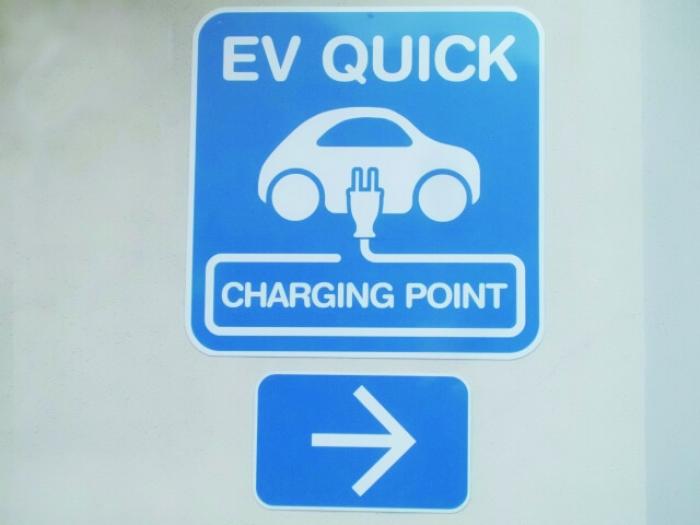電池の液漏れはなぜ起こる?電池の液漏れ原因、掃除方法、予防ポイントをまとめて紹介
電池から液漏れした液は素手で触ったり、目に入ったら危険です。そこで今回は電池が液漏れする原因や、液漏れを予防するポイントを紹介します。
電池が液漏れする原因は?

電池に白い粉が付いていたことはありませんか?
電池の使い方や保管方法を誤ると液漏れします。電池が液漏れする原因は、電池の仕組みに大きく関わっています。
電池は+極と-極の材料を電解液に入れることにより化学反応が起き、電流を発生させる仕組みになっています。もちろん、液漏れしない仕組みになっています。
しかし、使い方や保管方法を誤ると電池内部にガスが発生し電池内部の圧力が上昇します。圧力に耐えきれなくなった電池から、ガスと共に電解液が漏れ出してしまいます。
また、電池の通常放電が終わっているのに電池を交換しないと放電が続き、電池は過放電状態になります。この過放電でも液漏れします。
電池が液漏れする使い方
- 電池の向き(+-)を間違える
- 電圧の異なる電池(メーカーが異なる電池や、アルカリ電池とマンガン電池、古い電池と新しい電池など)を混ぜて使う
- 使い切った電池を機器に入れっぱなしにする
電池が液漏れする保管方法
- 電池を長期間放置する
- 電池の保管状態が悪い(湿度が高い、金属が電池の+-極に触れた状態など)
電池から液漏れしたの液体は危険

液漏れして電池から漏れ出した液体は電解液です。マンガン電池の電解液は、塩化亜鉛の水溶液の弱酸性で、目を傷つける可能性があります。
アルカリ電池の電解液は、水酸化カリウムで強いアルカリ性の液体で劇薬です。水酸化カリウムが皮膚に付いた状態で放置すると化学熱傷を起こす可能性があります。目に入ると失明の恐れがあります。
液漏れした液に触れた指に湿疹ができたり、液漏れした電池を舐めて嘔吐や頭痛を引き起こす事例もあります。液漏れした電池の取り扱いは十分注意しましょう。
液漏れした電池の正しい掃除方法と捨て方

液漏れした電池が入っていた機器や保管場所、家具、衣類にも液が付く場合があります。液漏れした液が付いた箇所の正しい掃除方法や、液漏れした電池の処分方法を知っておきましょう。
液漏れした液が付いた箇所の掃除方法
準備物
- ビニール手袋
- 雑巾2枚
- 綿棒
- サンドペーパー
- ビニール袋
液漏れの掃除手順
- ビニール手袋を着用し、液漏れした電池をビニール袋に入れる。
- 液漏れした液が付いた場所を濡らした雑巾でよく拭く。
- 細かい所は綿棒を使い、液漏れした液をしっかり拭き取るり、乾いた雑巾で乾拭きする。
- 液漏れした電池が入っていた機器の金具が錆びている場合はサンドペーパーで取る。
錆びている箇所はサンドペーパーで取る時は、金具がもろくなっている場合もあるため力加減に注意しましょう。サンドペーパーで取れない錆は機器の交換または修理にだしましょう。

液漏れした液が付いた衣類の洗濯方法
液漏れした液を水でよく流せば、他の洗濯物と一緒に洗濯できます。そのまま放置したり、液漏れした液を流さずに洗濯すると変色や劣化する可能性があります。
液漏れした電池の処分方法
液漏れした電池は、液漏れしていない電池と分けてビニール袋に入れて処理しましょう。電池の+-部分にセロテープやビニールテープを貼り、電流が流れない状態(絶縁)にすると安全です。
液漏れしている、していないに関わらず電池の+-部分が他の電池や金属に触れるとショートする可能性があります。ゴミ出しの方法は住いの自治体ルールに従ってください。電池の正しい捨て方については下記の記事で詳しく紹介しています。

電池の液漏れを予防するポイント
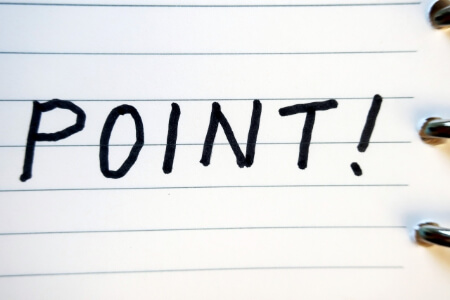
電池の液漏れを予防する使い方
- 電池の向き(+-)をよく確認して機器に入れる
- メーカーや種類が異なる電池を混合して使用しない
- 古い電池と新しい電池を混合して使用しない
- 使用していない機器は必ずスイッチを切っておく
- 定期的に電池を確認する
- 長期間使用しない機器の電池は外しておく
- 使い切った電池はすぐに機器から外して処理する
電池の液漏れを予防する保管ポイント
- 湿度の高い場所で保管しない
- 金属類と電池を一緒に保管しない
まとめ
今回は電池が液漏れする原因や、予防するポイントを紹介しました。電気が流れる電化製品やコンセントが傷んでいる場合や、電池を正しく使用しない場合は危険です。電池の液漏れとは異なりコンセントの増設や修理は自分ではできません。電気のお困りごとは資格を持ったプロに任せましょう。
地元の室内コンセント増設・電気スイッチの修理(交換)業者を探す
出張訪問サービスの検索予約サイトすまいのホットラインでは、高い技術を持った室内コンセント増設・電気スイッチの修理(交換)の専門業者が多数出店しています。
予約前に無料で質問ができ、作業料金や利用者の口コミも公開されているので、あなたの悩みを解決するピッタリの専門家を見つけることができます。

すまいのホットラインは、引越し・不用品回収・ハウスクリーニングなど、
200種以上の出張訪問サービスを予約できる、日本最大級の検索予約サイトです。
- 「相場」がわかる
- 総額料金や実際に利用した人の口コミで選べる
- 「人柄」で選べる
- スタッフの技術力や雰囲気・こだわりで選べる
- 「何でも」頼める
- どうすればいいかわからないお困りごとも解決