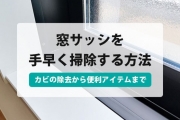窓掃除のやり方の完全版!新聞紙やウタマロクリーナーを使う方法や外側の窓掃除方法
毎年あっという間に迫ってくる大掃除…。窓掃除くらいは気持ちのいい秋頃からとりかかるのもいいですね。そこで今回は窓掃除のやり方や、窓ガラスに生えたカビの取り方を紹介します。
窓ガラスが汚れる原因は?

窓ガラスの汚れは、表と裏では汚れる理由が違います。
窓の表は土や砂で汚れる
窓の表は外に面しているので、土や砂汚れが多くなります。黄砂が飛んできた日などは、窓ガラスの汚れが目立ってしまいます。
また、自動車の排気ガスもススとなり窓ガラスを汚します。車通りの多いところに面した窓カラスは、土や砂の汚れの他に排気ガスの汚れも付きやすいです。
窓の裏はホコリや油で汚れる
窓の裏は室内に面しているので、部屋中の目に見えない細かいホコリが舞って窓ガラス付着します。キッチンで料理すると油が水蒸気となり、部屋中の窓ガラスに付着します。窓ガラスの汚れは油を含んだ汚れが多いです。
次に多いのが窓カラスの開け閉め時につく手垢です。特に小さい子供などは、窓ガラスを触りながら歩くので手垢がついてしまいます。
今はあまりいないかもしれませんが、部屋の中でタバコを吸う人がいるとタバコのヤニが窓ガラスに付着します。このように窓ガラスの表と裏では汚れの種類が違うので、汚れにあった掃除が必要です。
窓掃除しないとパッキンにカビが生えやすくなる

窓のパッキンはカビが繁殖する条件を満たしやすい場所の1つです。カビが好む環境は主に4つです。
- カビが過ごしやすい温度(10~45℃前後)である
- 湿度が高い(65%以上)
- 酵素がある
- カビの栄養源である水分・ホコリや汚れなどがある
結露の発生によりカビが好きな条件が揃ってしまうので、窓のパッキンにカビが生えてしまいます。窓のパッキンにカビが生えないようにするには条件を崩すことが必要ですが、それは「予防」のお話になります。
窓掃除するために必要な道具を揃えよう

準備物
- ゴム手袋
- レジャーシート
- 雑巾
- アルカリ性合成洗剤
- モップ
- ブラシ
- スポンジ
- ヘラ
- スクイジー(ワイパー)
- 新聞紙
- マイクロファイバー




レジャーシートは窓掃除する前に、床に敷いておくと洗剤などで床が汚れるのを防げます。
窓掃除する時に使う洗剤はアルカリ性の洗剤がオススメです。アルカリ性の洗剤は油汚れを落とすのが得意です。モップやスポンジなど使い汚れを落としますが、最後の仕上げはスクイジーで水滴を取り除くと水垢が付かずキレイに仕上がります。
洗剤を使用しないで窓掃除する場合は、新聞紙やマイクロファイバーを使っても汚れを落とせます。新聞紙のインクは油分や手垢の成分を分解し窓の汚れを落としてくれます。また、インクは曇り止めやツヤだし効果にもなります。
自分で窓や網戸を掃除する方法

窓ガラスの外側は一番汚れやすい場所です。窓掃除する前に網戸の掃除から始めましょう。曇りガラスの掃除方法については下記の記事で詳しく紹介しています。

網戸をアルカリ性合成洗剤で掃除する
準備物
- ブラシ
- スポンジ
- アルカリ性合成洗剤
- 雑巾
アルカリ性合成洗剤で掃除する手順
- 網戸に付いたホコリや汚れをブラシで落とす。
- スポンジに水を含ませて網戸全体を濡らす。
- スポンジにアルカリ性合成洗剤をつけて、下から上へこすり洗いして洗い流す。
- 雑巾を濡らして固く絞り、網戸の外側と内側を拭き完了。
中性洗剤で窓の表側を掃除する
準備物
- スポンジ
- 中性洗剤
- スクイジー
窓の表側を掃除する手順
- スポンジを使って窓に付いた汚れを取る。
- スポンジに水を含ませて窓ガラスを濡らす。
- 取っ手の気になる手垢はスポンジに中性洗剤をつけてこすり洗いする。
- 洗剤を洗い流し、スクイジーを斜めに移動させて余分な水分を取り完了。
スクイジーを平行に動かすと水滴の筋が残るので注意しましょう。
アルカリ性合成洗剤で窓の裏側を掃除する
準備物
- スポンジ
- アルカリ性合成洗剤
- 雑巾
- バケツ
窓の裏側を掃除する手順
- 窓の裏側に付いたホコリや汚れをスポンジで取る。
- バケツに水を入れてアルカリ性合成洗剤を少量入れて、雑巾を濡らし硬く絞る。雑巾で汚れを拭き取る。
- 洗剤が残らないように窓ガラスを水拭きする。
- 最後にスクイジーで斜めに移動させながら、余分な水分を取り完了。
ベランダがない窓を掃除するオススメ道具
雑巾やワイパーを直接手に持って窓掃除します。細かい汚れも目で確認しながら拭き取れますが、腕より長い距離は届きません。特にベランダのない窓は、外側の掃除が中途半端になってしまいます。少しでも遠い場所を拭くため部屋から身を乗り出したり、窓のレールにまたがって掃除するのは危険です。マンションの高層階では、バランスを崩して落下しケガではすまないことも考えられます。
また、窓から落としたワイパーや洗剤が、歩いている人に直撃してしまうリスクもあります。他人をケガさせてしまうのはより恐いので、なるべく身を乗り出す方法は避けましょう。身を乗り出さずに窓掃除できる掃除ロボットを紹介します。使用する時は説明書よく読んで掃除しましょう。




窓ガラスに生えたカビを取る方法

窓のサッシやゴムパッキンではなく、窓ガラスにカビが生えているのを見つけて驚いたという人もいるかもしれません。窓ガラスに生えたカビは、比較的簡単に落ちますのでご安心下さい。
準備物
- アルカリ性合成洗剤または食器用洗剤
- バケツ
- 雑巾
カビを取る手順
- バケツに水とアルカリ性合成洗剤を少し入れて混ぜる。
- バケツに雑巾を浸して絞り、窓に生えたカビを拭き取る。
- 乾いた雑巾でしっかり窓ガラスを乾拭きして完了。
食器用洗剤を使ってもいいですが、1本あると便利!と主婦の間で人気の「ウタマロクリーナー」もオススメです。

窓サッシの掃除方法とカビを取る方法

窓のサッシを毎日掃除する人はなかなかいないと思いますが、掃除機は毎日や2日に1回かける方がほとんどです。晴れの日は窓のサッシにも掃除機をかけてホコリやゴミなどを吸い取ってりましょう。毎日ではなくても週に1度か、2度するだけで、汚れがたまるのを防げます。
掃除機で吸い取るのが難しい端にたまったゴミは、古歯ブラシやつまようじで掻き出してから掃除機で吸い取ります。出勤前など忙しい時は無理せず週1回程度、時間のある時にやっておくのがオススメです。窓のさんを掃除する頻度や掃除方法については下記の記事で詳しく紹介しています。

窓サッシを掃除する
準備物
- 掃除機
- 古歯ブラシ
- 竹串または爪楊枝
- ペットボトル
- 食器用洗剤
- 雑巾
窓サッシを掃除する手順
- 掃除機を使って窓サッシのホコリやゴミを吸い取る。
- 掃除機で吸い取れない細かい汚れは古歯ブラシや竹串、爪楊枝でかき出す。
- ペッドボトルに水と食器用洗剤を少し入れてサッシに少しずつかける。
- 雑巾でサッシの汚れを拭き取り、最後は乾いた雑巾で乾拭きし水分を拭き取る。

窓サッシのカビを取る
カビを取るのに有効なのはエタノールです。エタノールにはたんぱく質を分解する作用があります。カビはたんぱく質などで構成されているため、エタノールを使えばカビを除去できます。
しかし、エタノールを使う時には火気厳禁です。部屋を換気しながら掃除するようにしましょう。また、塩素系漂白剤と混ぜると有毒なガスが発生するため注意しましょう。
カビを掃除する時は空気中にカビや洗剤が飛ぶこともあります。そのためゴーグルやマスクなどしておくと安心です。洗剤での手荒れが気になる方はゴム手袋をつけて掃除しましょう。
準備物
- 消毒用エタノール(80%以上のもの)※自宅に無水エタノールがある場合には無水エタノールと水を8対2の割合で薄める。
- 雑巾または布
- 割りばしまたは綿棒
- 掃除機
サッシのカビを取る手順
- 大きなホコリは掃除機で吸い取り、細かい汚れは割りばしに布を巻いた物や綿棒で取り除く。
- 消毒用エタノールを雑巾につけ、カビを拭き取って完了

サッシ修理する基準や業者に依頼するべき状態については下記の記事で詳しく紹介しています。

ゴムパッキンに生えたカビを取る4つの方法

窓のゴムパッキンの部分には水分が貯まりやすく、カビも生えやすい場所です。その上カビが奥まで根を張ると取るのが難しい場所でもあります。
塩素系漂白剤
準備物
- 塩素系漂白剤
- 新聞紙
- キッチンペーパー
- ラップ
- 雑巾
- マスク
- ゴム手袋
塩素系漂白剤でゴムパッキンに生えたカビを取る手順
- マスクやゴム手袋を装着する。
- 窓のゴムパッキンに付いたホコリや、汚れを雑巾で拭き取る。
- 床に塩素系漂白剤が付くのを予防するため、新聞紙を広げて敷いておく。
- 水に濡らして軽く絞ったキッチンペーパーを窓ガラスと、ゴムパッキンに貼り付けてゴムパッキンに塩素系漂白剤を吹き付ける。
- キッチンペーパーの上からラップで覆いパックして15~20分程度放置する。
- ラップとキッチンペーパーを剥がし、水に浸した雑巾を固く絞り水拭きする。
- 最後に乾いた雑巾でしっかり乾拭きして、しっかり水分を取り完了。

ゴムパッキン専用の塩素系漂白剤
準備物
- ゴムパッキン専用の塩素系漂白剤
- キッチンペーパー
- 雑巾
- マスク
- ゴム手袋
ゴムパッキン専用の塩素系漂白剤の使い方
- マスクやゴム手袋を装着する。
- 窓のゴムパッキンに付いたホコリや、汚れを雑巾で拭き取る。
- カビが生えているパッキンに、ゴムパッキン用のカビ取り剤を塗る。
- 15~30分程度放置する。(使用説明書を確認する)
- キッチンペーパーを剥がし、水に浸した雑巾を固く絞り水拭きする。
- 最後に乾いた雑巾でしっかり乾拭きして、しっかり水分を取り完了。
ゴムパッキン専用の塩素系漂白剤をパッキンに塗る時は、液だれを防ぐために水で濡らしたキッチンペーパーを貼っておくと安心です。

キッチンハイター
ゴムパッキン専用の塩素系漂白剤が自宅になく「代用品を知りたい…」という人には、「キッチンハイターと片栗粉」を使って、ゴムパッキン生えたカビを取る方法について紹介します。
準備物
- キッチンハイター
- 片栗粉
- 割りばし
- 雑巾
- マスク
- ゴム手袋
キッチンハイターの使い方
- マスクやゴム手袋を装着する。
- 窓のゴムパッキンに付いたホコリや、汚れを雑巾で拭き取る。
- 同じ量のキッチンハイターと片栗粉を割り箸などで混ぜてペーストを作る。
- ペーストをカビが生えているパッキンに塗り5分程度放置する。
- 水に浸した雑巾を固く絞り水拭きする。
- 最後に乾いた雑巾でしっかり乾拭きして、しっかり水分を取り完了。

キッチンハイターの使い方やキッチンハイターがNGな場所については下記の記事で詳しく紹介しています。

クエン酸と重曹
カビキラーやキッチンハイターなどを使用するのに抵抗がある人は、クエン酸と重曹を使って窓のゴムパッキンのカビを取る方法もあります。効果はカビキラーの方が上ですがカビの生え具合が軽い場合や、どうしても塩素系の洗剤を使いたくない方は試してみて下さい。
準備物
- クエン酸(粉末)
- 重曹(粉末)
- 空のスプレーボトル
- ブラシ
- 雑巾
クエン酸と重曹でゴムパッキンに生えたカビを取る手順
- クエン酸と重曹を粉のまま同じ量で混ぜ合わせたものをパッキンのカビに振りかける。
- 空のスプレーボトルに水をいれて粉の上から吹きかける。シュワシュワ発泡してくるので、そのまま30分程度放置する。
- 水に浸した雑巾を固く絞り、しっかり水拭きする。
- 最後に乾いた雑巾でしっかり乾拭きして、しっかり水分を取り完了。


このように窓のゴムパッキンに生えたカビを取る方法はいくつかあります。ご家庭にある道具に合わせて方法を選びましょう。なかなかカビが落ちない時には、何回か作業を繰り返しましょう。
窓掃除する頻度はどれくらい?

窓をキレイに保つには汚れたと気づいた時にこまめに掃除しましょう。窓の本格的な掃除は年末の大掃除と、6月~7月頃の年2回程度で十分です。半年に1回のペースで汚れを落とすと効率がいいです。
冬になると暖房や加湿器を使うようになるので、窓は外気との気温差が大きくなり結露が付きます。結露をそのまま放置すればカビが繁殖する原因になるため、窓ガラスや窓枠、サッシなども掃除すればカビ防止につながります。
6〜7月は花粉や黄砂が落ち着いてくる時期なので、窓掃除するのにちょうどよい時期になります。窓掃除は湿気があった方がガラスに付着した汚れが浮き出るので、曇りや雨上がりの朝や夕方がオススメです。窓掃除する日は天気がいい日や、日中にすると乾燥しやすいので拭き跡が残りやすくなってしまいます。また、光が反射してしまうと汚れが見えにくくなってしまうので、避けた方がいいでしょう。
窓掃除でやってはいけない事

窓掃除でやってはいけない事があります。それは窓掃除に洗剤スプレーを使う場合は、部屋の窓ガラス全部に吹きかけないということです。全ての窓に洗剤を吹きかけて掃除すると、液垂れの原因になります。
また、洗剤が乾燥してしまうと白くなってしまいます。ゴシゴシと力強く洗わないとうまく拭き取れなくなってしまい掃除に時間がかかってしまいます。洗剤スプレーは窓ガラスに直接スプレーするのではなく、雑巾やスポンジに吹きかけてから掃除しましょう。
窓掃除は窓1枚ずつ仕上げることをオススメします。乾いた雑巾で二度拭きしてしまうと、かえって拭きムラができます。また、窓に雑巾の繊維がつきやすくなってしまいます。乾いた雑巾の二度拭きはしないようにしましょう。
窓にカビを生やさないための4つの予防対策

定期的に換気する
窓やドアを開けて、なるべく密室状態を避けましょう。風の通り道を作ることで湿気を逃し、カビが生えにくい環境を作ります。
月に1回はエタノールで窓を消毒する
エタノールをかけるだけでも滅菌する効果があるので、カビの再発防止につながります。月に1回を目安にして定期的にするように心がけましょう。
エタノール水の作り方は、空のスプレーボトルに無水エタノールと水を8:2の割合で混ぜるだけです。換気して火のそばでは塩素系漂白剤を使わないように注意しましょう。
結露対策のグッズを使う
結露防止シートやスプレーなど結露対策の道具を使いましょう。窓にカビが生えるのは湿気だけが原因ではなく、湿気からできる結露もカビが生える原因になります。
そこで結露を防止すればカビは生えづらくなります。結露を防止するのに便利なのが結露防止グッズです。費用をかけないなら、新聞紙を窓に張り付くだけでも十分効果的です。



除湿機を使う
梅雨の時期などは部屋干しをする回数が増えます。部屋干しすると部屋の中の湿気も増えて、カビが生えやすくなります。部屋干しする時は除湿機や、エアコンにある除湿機能を使いましょう。
全てするのは難しいかもしれませんが、1つするだけでも効果が違ってきます。できることはやりましょう。
まとめ
今回は窓とサッシを掃除する方法や、窓とサッシに生えたカビを取る方法について紹介しました。長年蓄積してしまったカビが取れなかったり、仕事で忙しくて掃除にかける時間も体力もがない時や家事がどうしても苦手という人もいます。そんな時は業者に依頼しましょう。
気になった汚れやカビを放置してさらに悪化させるよりも、プロの力ですっきりキレイに掃除してもらえば気持ちも家も明るくなります。業者が使う洗剤や掃除方法は、一味違うので素人では落としきれないカビや汚れをキレイに取り除いてくれます。
地元の窓・サッシの掃除業者を探す
出張訪問サービスの検索予約サイトすまいのホットラインでは、高い技術を持った窓・サッシの掃除の専門業者が多数出店しています。
予約前に無料で質問ができ、作業料金や利用者の口コミも公開されているので、あなたの悩みを解決するピッタリの専門家を見つけることができます。

すまいのホットラインは、引越し・不用品回収・ハウスクリーニングなど、
200種以上の出張訪問サービスを予約できる、日本最大級の検索予約サイトです。
- 「相場」がわかる
- 総額料金や実際に利用した人の口コミで選べる
- 「人柄」で選べる
- スタッフの技術力や雰囲気・こだわりで選べる
- 「何でも」頼める
- どうすればいいかわからないお困りごとも解決